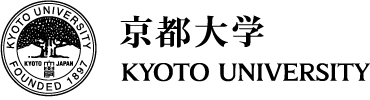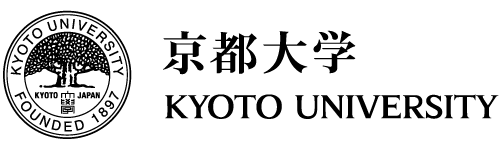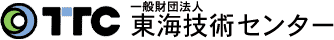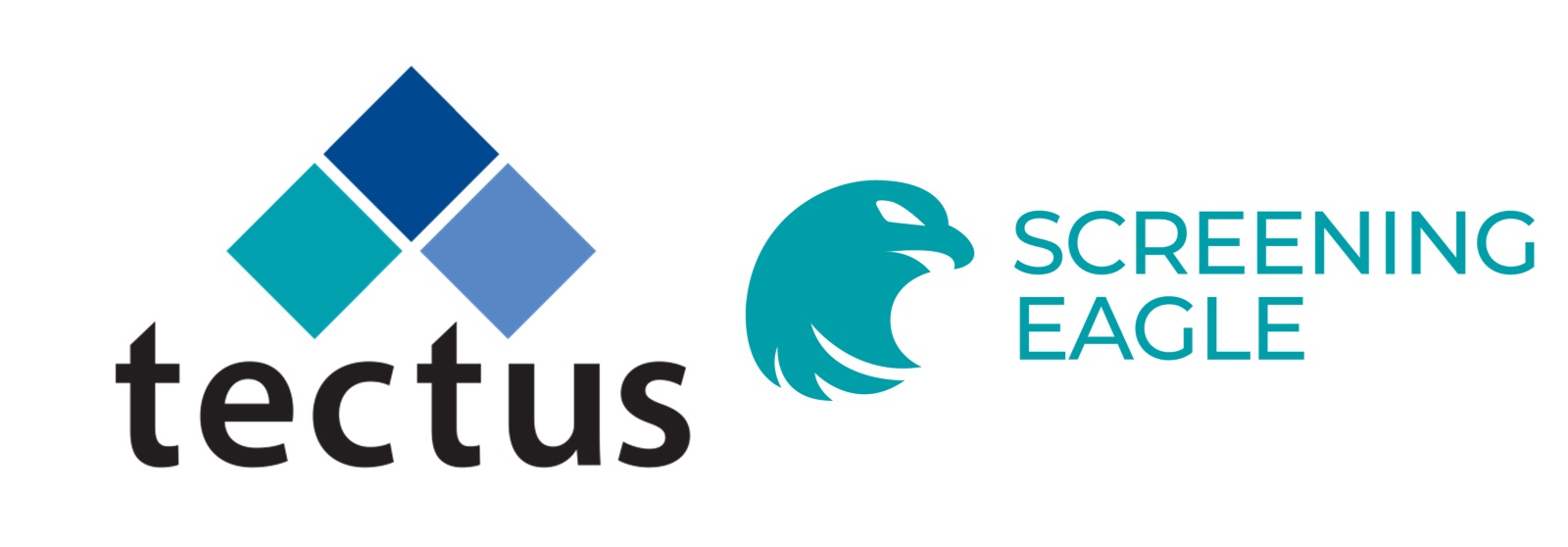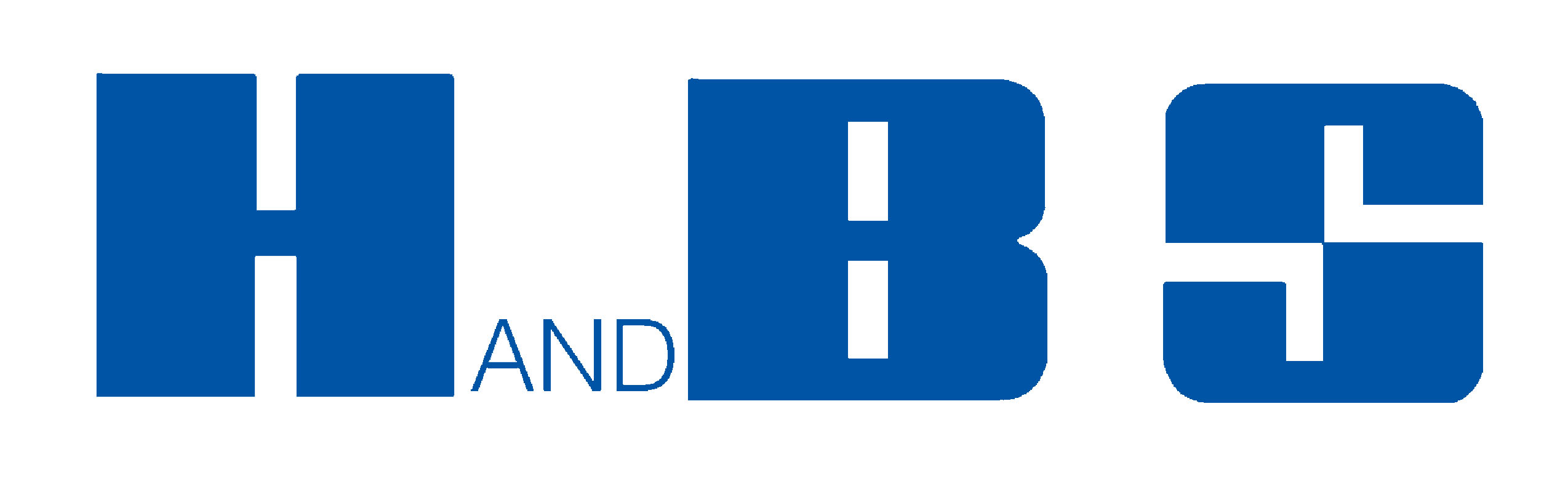インフラ先端技術産学共同研究部門についてABOUT ITIL
破壊的異能 [INNO]vationにより次世代インフラシステムの構築へ
融合 fusion, 結合 combination, 連携 tie-up/ cooperationそして,協業 collaboration

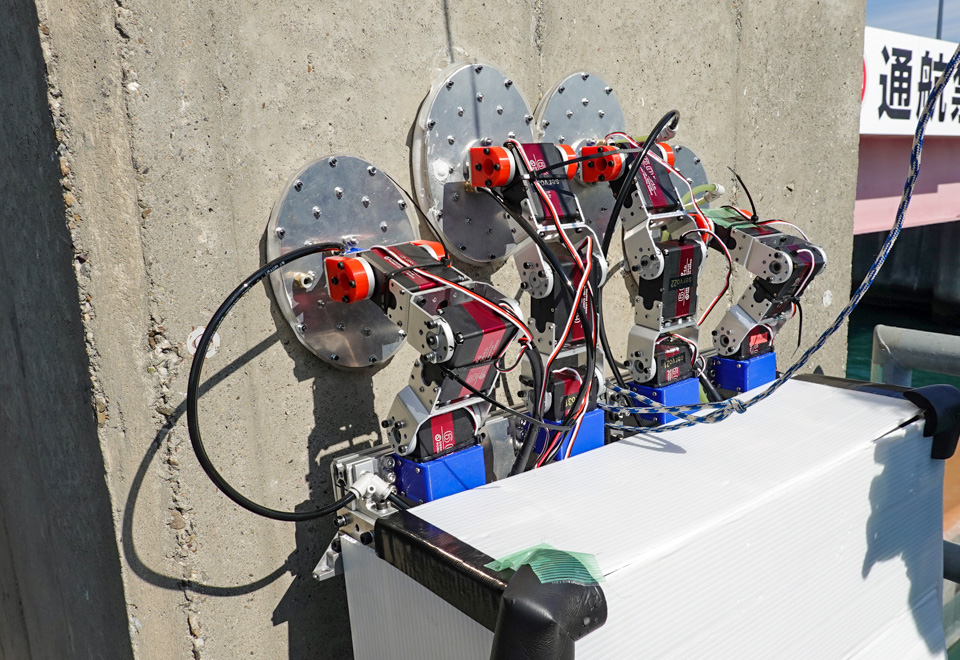

平成26(2014)年4月に可視化できない土木構造物内部の劣化を調査診断できる先端技術を研究開発する場として共通の問題を有する西日本高速道路、阪神高速道路および、両者のエンジニアリング会社が中心となり、当時社会基盤工学専攻宮川豊章教授を本学の代表者、白土博通教授(故人)、塩谷智基特定教授を運営委員として「インフラ先端技術共同研究講座」が設立された。
本講座は同時に、国家プロジェクト「SIP、戦略的イノベーションプログラム(内閣府)」、「RIMS、道路インフラモニタリングシステム、NEDO」、「大規模インフラ向け高性能振動発電開発、NEDO」、「COI センターオブイノベーションプログラム、JST」に参画する機会も得て、3期6年間にわたる2019年度まで道路インフラを中心に革新的な検査・診断手法を中心に多くの実績を上げてきた。また、これらの特異技術は、民間道路会社維持管理フローへの導入検討がなされているほか、京都府、富山市などの自治体とも技術連携し、自治体管理構造物への活用も試みられている。さらに、ドナー側の合意を得て、国内外の研究機関を含め、電機メーカー、建設会社、建設コンサルタント、計測会社をはじめ他大学との連携研究も積極的に実施してきた。また、同じ課題に挑む海外研究機関との研究交流も精力的に図り、これまでブリュッセル自由大学、エジンバラ大学、スイス連邦工科大チューリッヒ校、リュブリャナ大学(スロベニア)、香港理工大学、マラヤ大学、トリアッティ大学(ロシア)、深圳大学などから研究員を受け入れ共同研究を実施してきた。
2020年度には、本講座が中心となり、本学工学研究科で初めての公式コンソーシアム「インフラ先端技術コンソーシアム」が設立された。コンソーシアムは、革新的な検査・診断技術を確実に実装し、点検・診断・措置・記録の維持管理サイクルに導入するための、蓄電、電送技術など土木分野以外の課題に対応できる分野横断型の組織で、本講座はこれまで、西日本高速道路、西日本高速道路エンジニアリング関西、鷺宮製作所、IPH工法協会、東海技術センター、藤村クレスト、CORE技術研究所、東芝、大日本ダイヤコンサルタント、大成建設、ニューブレクス、オートデスク、水資源機構、日本ピーエス、エッチアンドビーシステム、中日本高速技術マーケティング、JFDエンジニアリング、IHI検査計測、Nix JAPAN、物質・材料研究機構、量子科学技術研究開発機構をパートナーとし、様々な課題の研究開発を担ってきた。令和5(2023)年11月には、国家プロジェクト「SIP、戦略的イノベーションプログラム(内閣府)」第3期である「スマートインフラマネジメントシステムの構築」に参画する機会を再び得た。また、令和6(2024)年4月1日より、京都大学内で新設された成長戦略本部に所属を移し、「インフラ先端技術産学共同研究部門」と名前を改めることになった。今後も更なる早期社会実装を目指して鋭意に取り組んでいく。